
2022年2月24日(木)ロシアが隣国ウクライナに軍事侵攻してから4年。イスラエルガザ地方の紛争、アメリカによるイランやベネズエラへのミサイル攻撃など、世界の平和が大きく揺らいでいます。
子どもたちには、そんな大人たちの行動が理解ができません。どうして、大人なのに仲良くできないのか…。大人たちが教えている「仲良くする」って、どういうことなのか…。
大人たちは子どもに嘘を教えているのか…それとも大人は嘘つきなのか…。
子どもたちが観ています。わたしたち大人の姿を…
2020年5月のブログ積光成輝に「北欧の特別支援教育」(https://www.hikarinoko-kai.or.jp/2020/05/14/569/)を掲載しました。

私が北欧を訪ねたのは2008年ですから、今から14年前になりますが、ヨーロッパでは当時からインクルーシブ(統合)教育が当たり前に行われていました。
我が国ではようやく昨年から5年を掛けて通常学級の児童生徒数を35人に引き下げようとしていますが、2008年当時既に先進各国では25人学級・複数担任制を実現していて、殆どの学級に障礙のある子どもと特別支援専門教諭が配置され、全ての公立小中学校で特別支援専門教育を受けられる体制が整っていました。
そういえば当時から日本の教育制度の遅れが指摘されていたなぁ…と、改めて思い返したことでしたが、そういう意味においてはこの度の国連の勧告は、ヨーロッパ先進各国からは『遅きに失している』と見られているのかもしれません。

何故、2022年9月9日に国連から日本政府に対して「インクルーシブ教育の権利を保障すべき」との勧告が発せられることになったのか。それは、2006年に国連が採択した「障害者の権利に関する条約(以下、障害者権利条約)」を、2014年に我が国が批准(ひじゅん)したことによっています。
当然のことながら批准をしたからには、障害者権利条約を国の政策などに反映していく必要がある訳ですが、8年を経過してもなお“分離教育(障礙児と健常児を分けて教育すること)”を改めようとしない日本政府の対応に、国連が業(ごう)を煮やしたということなのでしょう。勧告に先立って1ヵ月以上前に日本から障礙当事者・関係者100人余りがジュネーブに呼び寄せられ、権利委員が日本の現状を聴取したと伝えられていて、批准後の政策への反映が不十分と判断されたのだろうと考えられます。
冒頭で紹介したブログ記事にも書いた通り、14年前に北欧の特別支援教育の現状を視察して『夢のようだ』と感じましたが、税制を改革しない限り我が国では実現不可能と諦(あきら)めていました。しかし、今回の勧告を受け、税制の問題ではなく人権意識の問題であると改めて思い知らされました。
日本では各地に立派な特別支援学校が建てられ、障礙児童・生徒が日々何台ものスクールバスで遠方から集められて来ます。一見すると十分な予算が投じられ、大変整った学制制度であるようにも見受けられますが、当事者の立場に立ってみれば、障礙があるだけで幼い頃から地域の子ども達と一緒に遊んだり学んだりできない生活を長きに渡って強いられているとも言えます。そうした我が国の施策の在り方に、国連がNo!を突きつけた訳です。但し、こうした問題は国連の鶴の一声だけで一朝一夕に変えられるものではありません。国民の間に理解を拡げながら、文化として醸成していくことが求められるからです。
毎年12月に発行の「ひかりのこニュース」やホームページでもお示ししている通り、社会福祉法人光の子会の基本理念は「光の子として歩みなさい(聖書エフェソの信徒への手紙5章8節)」ですが、その主題は「共に生き、共に生かされる」です。
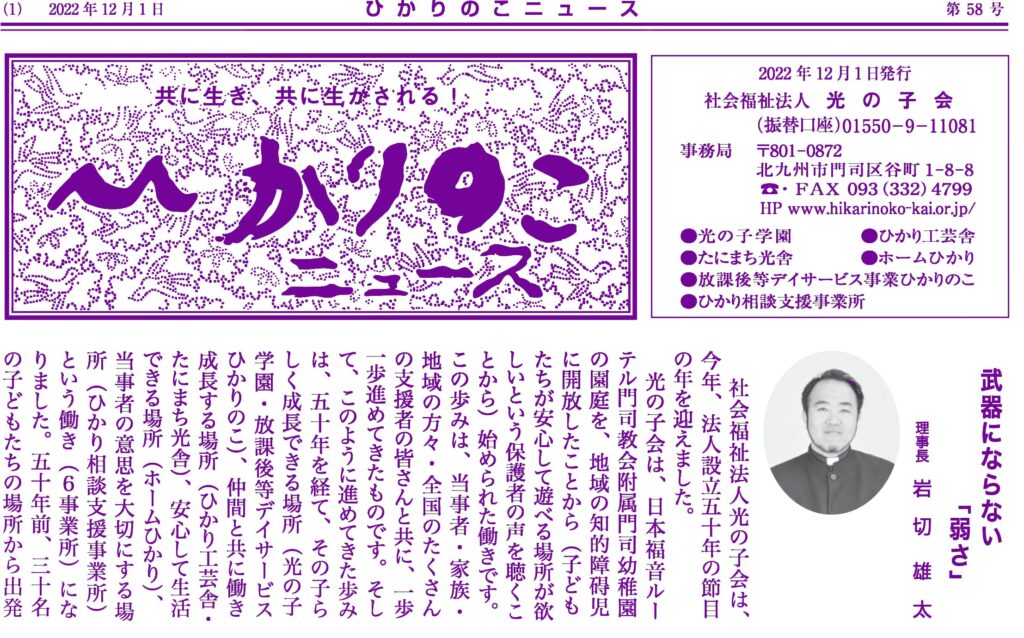
“障礙の有る無しに拘(かか)わりなく、共に神様に命をいただいた者同士が手を携えて支え合いながら生きていこう”と、2019年の「ひかりのこニュース」からは「障害をもつ子と共に生き、共に生かされる」の斜体太字部分を除いて、現行に改めています。また、ホームページに「障礙(がい)ある人々の人間的生活の充実を図るために支援し、家族および地域の方々と協同して、障礙の有無にかかわらず共に暮らしやすい社会と文化の創造を基本的使命とします」と掲げる通り、北欧で実践されているインクルーシブは、私たち法人の理想を具現化した一つの形であるとも言えるのです。
少し話は逸れますが、「施設」は、元々は仏教の用語で「施設(せせつ)=この世に存在しないものを仮に存在するものとしてこう呼ぶ」と、本来は“概念”を意味する言葉でした。
私はこれを知った時から、福祉施設もかくあるべきなのではないかと思ってきました。私たちが理想とすべきは、福祉施設を必要としない世界、病院施設を必要としない世界、警察・軍事施設を必要としない世界を構築することであって、これらは必要な期間にだけ設けられる“仮”であるべきなのだろうと。勿論、これは極論で、現実にはこれら無くして社会が成り立たないことは重々承知していますが、だからと「理想は理想」と机上の空論にしてしまうのではなく、少しでもその理想に近付こうとする努力を、私たちは忘れてはならないと思うのです。
この度の国連の勧告は、我が国の教育界のみに投じられた一石ではありません。障害者権利条約を下敷きとして、社会のあらゆる場面で障礙のある人たちが“分離されない”ことを求める最初の波紋に過ぎないからです。まず教育界から始め、学校の中で、職場の中で、地域の中で、障礙ある人たちと当たり前に触れ合える社会となることを目指し、改革が進められていくことになるでしょう。そうでなければ、我が国は障害者権利条約の批准を撤回せざるを得なくなってしまいます。
今後、効率主義、能力主義、経済至上主義の競争社会から、どのように脱皮し次なるステージへとステップアップしていけるのか、そのことが問われています。
案外と、その答えを握っているのは、当園の園児のような子どもたちなのかもしれません。子どもたちの手を開いて、どんな答えが握られているのか覗いてみましょう…


※2022.5.31ブログ積光成輝 発達18「発達と臨界期」(https://www.hikarinoko-kai.or.jp/2022/05/31/2849/)にも記述した通り、脳が著しく成長・発達する幼児期については、早期発見・早期療育(発達支援)の観点から、力を最大限に引き出すことのできる児童発達支援センターなどの専門機関で療育・発達支援を受けられることを推奨いたします。